| てぃーだぬふぁー通信 第14回 - 未成年の飲酒について 西原 廣美 教育長 |
◆地域教育情報 『 てぃーだぬふぁー通信 』 は、学校・PTAと地域を結び付ける社会教育活動として行っています。どうぞ宜しくご愛読ください。 |
| |
 浦添市教育委員会
教育長 西原廣美 |
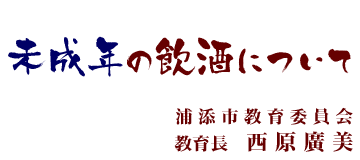
次代を担う青少年がたくましく、心身ともに健やかに育つことは、市民誰しもが思う願いであります。
それと同時に、そのように育むことは、私達大人に課せられた大きな責務でもあります。
「子は親の背中を見て育つ」と云います。
感受性豊かな子ども達は大人のしていることを良く観察しているものであります。大人のしていることを真似たがるものであります。
そういうことからいたしますと、青少年を健やかに育てる為には、私達大人が先ず襟を正し、子ども達の模範とならなければなりません。
改めて紹介するまでもなく、本市の子ども達の殆どはスポーツや芸術・文化面をはじめ、様々な分野において全国レベルの活躍をする素晴らしい子ども達であります。
しかしながら、刑罰に触れる行為をした14歳未満の少年いわゆる触法少年や侵入盗犯や粗暴犯少年等、家庭や学校、地域社会に適応できない子ども達が増えてきていることもまた事実であります。
ちなみに、本市の深夜はいかいや飲酒、喫煙、家出等で警察に補導された件数は、8月末現在2,393人で、行為別では飲酒が231人、喫煙481人、深夜はいかい1,586人等となっており、とりわけ深夜はいかいで補導される少年がかなり多くなっています。
また、昨年(2006年)一年間に県内で飲酒によって補導された少年は、4,065人もいて、少年の人口千人当たりの補導人数に換算すると、16.5人となっていて、全国平均1.7人の9.7倍と二年連続で全国ワーストであると云います。
今年は、中・高校生が飲酒によって補導された事件が、夏休み辺りから急激に増えてきていて、連日のようにマスコミで報道されています。
酒類を中・高校生が自宅から持ち出してきたケースや通行人に依頼して購入したケース、はたまた自宅で明け方まで飲酒しているのを親が容認したケース等々、エスカレートする一方であります。
このように、未成年者の飲酒については、ひとり子ども達だけに起因するのではなく、私達大人のモラルの低下にも大きく起因しているのであります。
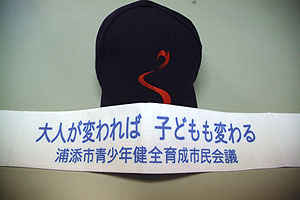 「大人が変われば
子どもも変わる」
浦添市青少年健全育成市民会議のハチマキ |
また、子ども達の飲酒行動の殆どが深夜に行われていることを考えると、本県の悪しき慣行である「夜型社会」を改めない限り根絶することは難しいと思うものであります。
県外においては、9時、10時以降、こうこうと電灯が輝いている光景や子ども達が街をうろついている光景は、大都会以外はあまり見かけないのですが、沖縄はどうでしょう、繁華街以外でもよく見かける光景であります。
私は、少年非行の是正のみならず様々な犯罪を防止する為には、先ずこの夜型社会を改善しなければならないと常々思っています。
また、最近良く見かける事象として、居酒屋に子ども連れで訪れる大人達がいることがとても気になっています。
まるで、居酒屋を食堂かファミリーレストランとでも思っているかのようで、首をかしげたくなります。
そのことを悪いと思うのは、果たして私だけでしょうか。
本県の青少年の飲酒による補導件数の増加と居酒屋へ子どもを連れていくという慣行とが果たして無関係と云えるでしょうか。私は決して無関係ではないと思います。
 青少年を健やかに育てる浦添市民総決起大会において
西原教育長より、青少年の深夜はいかいや未成年の
飲酒の防止を呼びかける激励のあいさつがあった |
先述したように、子ども達は、親や大人の背中を見て育つものであります。
親や大人達が美味しそうに飲酒したり、酔って楽しそうに話し合ったりしている光景を子ども達はどう見ているのでしょうか。酒は美味しいものだ、飲んだら楽しくなるものなんだと思い、知らず知らずの内に、飲酒に対する感覚が麻痺してくるのは至極当然のことではないでしょうか。
新聞報道によると、「未成年者の体はアルコールを分解する仕組みが未熟で、飲み始める年齢が早い程依存症になりやすい。記憶をつかさどる脳の神経細胞を破壊する危険性がある。」と云います。
また、16歳で飲酒していた人は、飲酒していなかった人に比べ、アルコール依存症、不法薬物使用、罪を犯すといったリスクが1.4倍から1.9倍にもなると云います。
 青少年を健やかに育てる浦添市民総決起大会において
「青少年の深夜はいかい防止 県民一斉行動」が確認された
(平成19年10月12日) |
先頃、県議会において「未成年者の飲酒防止に関する宣言決議」が可決される等、改善にむけた取り組みがなされつつありますが、それを全県的運動に広げていかなければ、その効果は期待できないと思います。
そこで、市民の皆様方にお願いを申し上げたいと思います。
「シンデレラタイムの励行」と「居酒屋に子ども達を連れていかない運動」を展開していただき、未来の浦添、沖縄県を担っていく大事な子ども達を飲酒から守り、心身共に健やかに、そしてたくましく育ててまいりましょう。
結びに、浦添市内の犯罪発生件数が昨年の同時期に比べて大幅に減少しているようです。
それもこれも、警察当局や地域住民、各種団体・機関等のご努力もさることながら、浦添市の産業振興センター・結の街のホームページ『ビジネス・モールうらそえ』の事件情報や不審者情報の発信による影響が大であると、常々評価をしているところであります。
この度、当ホームページに投稿する機会をいただき『未成年者の飲酒について』市民の皆様に呼びかけることができましたことは望外の喜びとするものであります。
どうか、今後とも地域の総合ポータルサイトとして、事件情報をはじめ各種の生活に密着した情報をタイムリーに発信していただき、浦添市の振興発展ならびに安心・安全な都市づくりにご貢献いただきますようご期待申し上げます。 |