 |
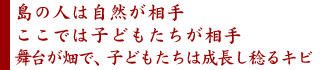
てだこホールのこけら落とし公演「太陽の王子(てぃーだのおうじ)」を演出したのが、演出家の平田大一さん。
舞台は、浦添ゆいゆいキッズシアターの子どもたち約70名が出演して見事な演技を披露し、大成功でした。
平田さんが手がけたうるま市の中学・高校生による現代版組踊『肝高の阿麻和利』は2000年の初演以来、'07年2月には第100回目の公演を達成。経済効果は概算で1.7億円とも言われています(参考資料/琉球新報・けいざい風水)
今回は、小浜島での暮らし生活そのものが詩人的な生活そのものと語る南島詩人・平田大一さんが舞台の上で子どもたちを相手に感動の種を蒔く演出力の源(キビ刈り援農塾)についてのお話を聴かせていただきました。
そして、沖縄の新しい産業の形「感動産業クラスター構想」を提案し、タオファクトリーを立ち上げるまでの平田さんのインタビューをどうぞお読みください。
≫ 第1回目のインタビューはこちらから |
古くて新しい芸術的な島の生活
舞台で学んだものを周りに広げていく子ども達
「自分が生まれた小浜島での暮らしというんでしょうか。僕は南島詩人という名前で詩の創作活動をやっているわけですが、それは、島の人の生活そのものが詩人的な生活だと思っているからなんです。潮の干満、気圧の高低、月の満ち欠けを読みながら自分達の暮らしを立てていく。そこにはタイムカードも週休二日もなければ、生きることイコール仕事、働くことであり、働くっていうことがそのまま自分の生き様だったりするし、それが芸術作品だったりするわけですよね。そういう面では、僕は新しい生き方ではなくて、むしろ島の人が昔やってた古い生き方を、たまたま田畑の代りにホールがある感覚でやっている。昔の人達の方が古くて新しいんだと。
島の人は自然が相手、ここでは子どもが相手。僕は人作りは種って言ってますんで、ホールが畑で、子ども達がキビ1本ずつに見える時があるんですね。『あ〜キビが育ってる育ってる、稔ってる稔ってる!これはいいなあ』と(笑)。
台風も来れば旱魃もあれば、それでキビは伸びていくわけで、そういった面では僕の町づくりとか町起こしっていうのは、島の中に答があるというか。答は元々そこにあるけれども気付いていない。その気付きの作業をさせるのが僕の仕事だと思っているし。」 |
島で当たり前のものが世界から見ると刺激的
元からあるものをジョイントさせて新しい光を当てる
「僕は大学を卒業して22歳から8年間、ちゅらさんが来るまで小浜で、実家の民宿うふだき荘をやりながらキビ刈り援農塾をしていました。キビ刈り援農塾というのは、宿泊料を無料にするかわり労働力を提供して欲しいということで始めたものです。初日に手の皮をむいて、三日で肩の皮をむいて、一週間で心の皮をむきたい人集まれと全国に呼びかけました。今年で13年目になりますね。僕が小浜を出てからも続いていて、名前も援農塾から小浜島ふるさと農業倶楽部に変わりました。昨年父親が亡くなったので、一旦閉塾したんですが、今年の8月にまたオープンする予定です。体験型の民宿は、あの頃はうちしかやっているところはなかったです。僕がずっとやってることっていうのは、今、島が、沖縄が必要としていることを、
ひたすらやっているだけなんです。」
|
「援農塾も、農業と観光のジョイントということを考えた時に、必然的にうちには民宿があってキビ畑があって、それしかできなかったんです。普通だったら『何もないんだよね、これしかないんだよね』と言うんですけど、じゃあこれとこれをジョイントさせると、こういうふうな新しいことができますよ、というのが僕の提案なんです。だから決して新しいものじゃないですよ。元々あったものを、光の当て方やアプローチを変える。例えば18年前に作った『ミルクムナリ』という曲もそうです。島にあった古いものを、日出克さんと一緒に唄って踊れるようなものにしようということで口説ち(くどぅち)を入れると。島では古いもの、当たり前のものが世界から見たら刺激的なんじゃないか、やってみせよう、というのが『ミルクムナリ』のコンセプトだったんです。
だから英祖にしても阿麻和利にしても察度や八重山のオヤケアカハチにしても、全部島にある古いものですよね。それを光の当て方を変えアプローチの仕方を変えて演出をしてあげると、見事に生まれ変わり再生してくれるんです。キビ畑も、キビ刈りはもうみんなイヤだイヤだって言うから、じゃあ楽しいキビ畑をプロデュースしてみようというのが、南島詩人農場という名前で始めたキビ刈り援農塾なんです。当時は10人ほどだったのが、今は年間延べ2000人来ますよ。キビが終わったら次は黒ゴマとかモズク、島らっきょうなど、収穫物の期間が変わりますから、3ヶ月とか半年間いる人もいますよ。僕は島起こし島作りというのは、島の人だけじゃなくて、島の外の人も一緒になってやるべきじゃないかなあという思いがあります。そうじゃないと、目線が片っ方だけの視点になってしまう。」 |
|
「今、子ども達に地域のことを一生懸命やってもらってますけど、僕は一流の島ンチュが一流の国際人だと思うので、地域で学んだものを基にして、世界に発信していく。視点は郷土だけど視野は世界へというか、そういうリーダー作りが子どもにとって大事なんじゃないかと思います。芸能人や有名人を作ることが目標ではなく、地域のことを良く知る子ども達を作る、それを育む場所が舞台ということです。そのシステムが今の僕のやり方なんじゃないかと思います。卒業した子ども達が成長して、学校の先生になりたいとか、保育士や介護福祉士になりたいと思った時に、自分たちが子どもの頃に学んだものや経験が活きてくるのだと思います。」 |
タオファクトリーを立ち上げる
沖縄の新しい産業の形「感動産業クラスター構想」
 |
「事務所は2005年にオープンして3年目です。有限責任中間法人タオファクトリーというんですが、簡単にいうと有限会社とNPO法人の間、という感じの組織形態です。社会起業家(social
entrepreneur/ソーシャルアントレプレナー)と言って、地域活動や文化教育活動はボランティアで行なうもの、みたいなイメージがあると思うんです。でもそうじゃない。活動は継続しないと意味がないから、そのための自主財源を作り出す、継続可能な事業を作り出すということが命題です。それを行なってきたからこそ、阿麻和利は9年目、浦添は8年目というふうに継続できているのです。
これがほんとの意味でのボランティアだったら継続はむずかしいですよ。10年なんてむずかしい。自主財源を作り出すシステムというのが大事で、それはNPO法人の寄付に頼るというのとは違う。有限会社のように利益を追求できるけれど、それが地域に還元できている社会性のある活動と、利潤を還元していくということと両方あるので中間法人という名前なんです。有限会社というのは利益追求がメインですけど、大きな意味で地域に『還元していく』という仕事が利潤に繋がっている。利益を生み出すことに繋がっているのであれば、これこそほんとに循環型の事業になってくる。
これはまだ日本でも珍しいやり方です。ですから竹中大臣が『文化でもって地域再生をかなえている先行的な事例の一つです』と何回も足を運んで来られたんです。沖縄ではあまり知られていないかもしれませんが、県外の方が注目しているのは間違いないと思います。子どもの舞台だからとか、若い人が元気にやっているねという話ではなくて、沖縄ならではの新しい起業の形・新しい仕事の形なんじゃないかと僕は思ってるんです。
それこそ基地に代わる次の産業というのは、まさに感動体験を軸にした文化産業というか、よく感動産業クラスター(ぶどうの房/同種の物や人の集合体のこと)構想と言うんですが、今、沖縄は健康産業クラスターなんですよね。その前はIT産業クラスターだった。次の沖縄の命題が何かというと、文化産業なんですよ。でも文化産業というくくりだと、芸能・音楽になっちゃうじゃないですか。沖縄は空手も古武道もあるし、スポーツも盛んですよね、マラソンも人がいっぱい集まるし。つまり、スポーツや文化芸能も含めて感動体験ができる産業、感動体験型産業を略して感動産業と言うんですけど。それを感動産業クラスター構想と呼んで、僕はそれを主軸にしていろんな仕事が生まれてくるという形が、沖縄の新しい仕事の形なんじゃないか、という提案をずっと県に対してもやっている。それの実践的な事例なんですよ。」 |
|
次回に続く
(平田さんのインタビューを3回に分けてお送りしています。次回が3回目。乞うご期待下さい。) |
