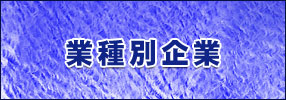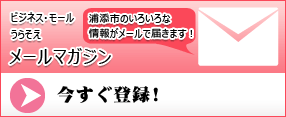HOME > 特集 > こころのオアシス > あぁ、ぼくらのマドンナが…
あぁ、ぼくらのマドンナが…
|
− 第5回 – |
 |
下地幸夫 (しもじ ゆきお)
1963年生まれ 浦添市出身 |
トレッキング中、山の中で、もよおしたときは、トイレなんてどこにもないから、ほとんど野小便、野グソになる。そんなとき、女の人はとても困るんだな。数キロ先の公園やダムのトイレに連れて行ってくれ、と突然言い出したりする。また、キャンプをする場合も女性はトイレがあることを条件にするのだ。わからない訳でもないが、女性にはわるいけど、ここは山の中、誰も見てないのだからそこら辺でちょっとしてちょうだいと言いたい気にもなる。ぼくら男は、山の中の生理現象はしかたないサーと思っているから、小便はすぐその場で、大の場合はちょっと森の中へ失敬という感じで穴を掘ってさっさと済ませてしまう。でも、男どもは本能的に女性の頼み事には当然かなわないので言うとおりにせざるを得ない。
 |
もう結婚して辞めてしまったが、昔、ぼくが勤めていた職場に美しい女性がいた。初めて彼女に会った男は誰だってあこがれを抱かざるを得ない、そんなマドンナ的な女性だった。でも、外見とは裏腹に男勝りの活発な性格で、それもアウトドアが大好きで、野山を駆け巡っていた。彼女以外は男だけといったキャンプに紅一点で参加しても全く憶することもないし、男たちと一緒に同じテントで寝ることも平気だった。嫁入り前のうら若き美しい女性が、である。でも、用を足したいときは男みたいにみんなの居るところで、ちょっと失敬と言って背を向けてするわけには、さすがの彼女もそれはできなかった。
冬のある晩のこと、男3人と彼女とで真夜中のやんばるトレッキングを楽しんでいたときだった。林道を歩いていて彼女がオシッコがしたいと言い出した。誰かが「この道のあのコーナーを曲がった所がここから見えないからやってもいいんじゃない。今夜はこの道を車1台しか通ってないから大丈夫だはずよー」と言っているのに最後まで聞こうとはせずに、彼女は「あのコーナー」のフレーズだけを聞くと小走りで懐中電灯片手に闇のコーナーの中に消えて行った。
 |
虫の音と星空が何とも言えず、それらが静かな夜を演出している。我ら男3人は地べたに座り込んで彼女が来るのを待ちながら冷えてキリッと澄んだ空気を満喫していた。そんな休息も束の間、林道の闇の向こうから何やら車のエンジン音らしきものが近づいてくるのを感じた。「この音は…、聞こえているのは僕だけじゃないよな」と確認しようと隣のヤツの目を見たときには、もうその音は軽く地響きを立てるくらいに大きくなっていて、確かめるまでもなくそれは自動車のタイヤが路面を叩くそのものである。それももうかなり近づいている。彼女が行った方向から聞こえてくる。コーナーから懐中電灯の明かりがジグザグに揺れながら猛スピードでこっちのほうへ向かってきた。その後を追いかけるように自動車のヘッドライトがその彼女の背を煌々と照らし、まるで映画「未知との遭遇」で使われていた映像効果を目の前で見ているような感じだった。
彼女の顔は今にも泣きそうな状態になっていた。車の中にいた二人の男は、我々の横を通り過ぎるとき、一体全体何があったんだ、と言いたげにお目めがかなりまん丸になっていた。そりゃそうだ。彼らはこの真夜中、誰もいないはずと思っている林道で、暗闇に、若い女性の白いケツが突然ヘッドライトの中に浮かび上がってきたのだから…。
この晩のこの林道を通る最初の自動車がよりによってこんなときに来るという、何てタイミングの悪さ。おかしくて腹が痛くなっているぼくらの横で、普段男勝りでならしていた彼女は、少しは女性らしさを取り戻したらしく、しばらく恥ずかしくて口が利けないようだった。
カテゴリー [こころのオアシス]





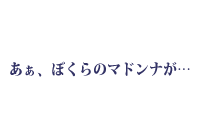
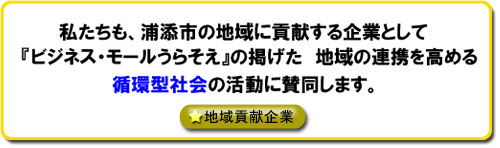
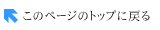
 浦添警察署からのお知らせです。
浦添警察署からのお知らせです。 台風や津波などの自然災害に関する防災情報
台風や津波などの自然災害に関する防災情報 不審者情報です。
不審者情報です。